
この記事を書いた人
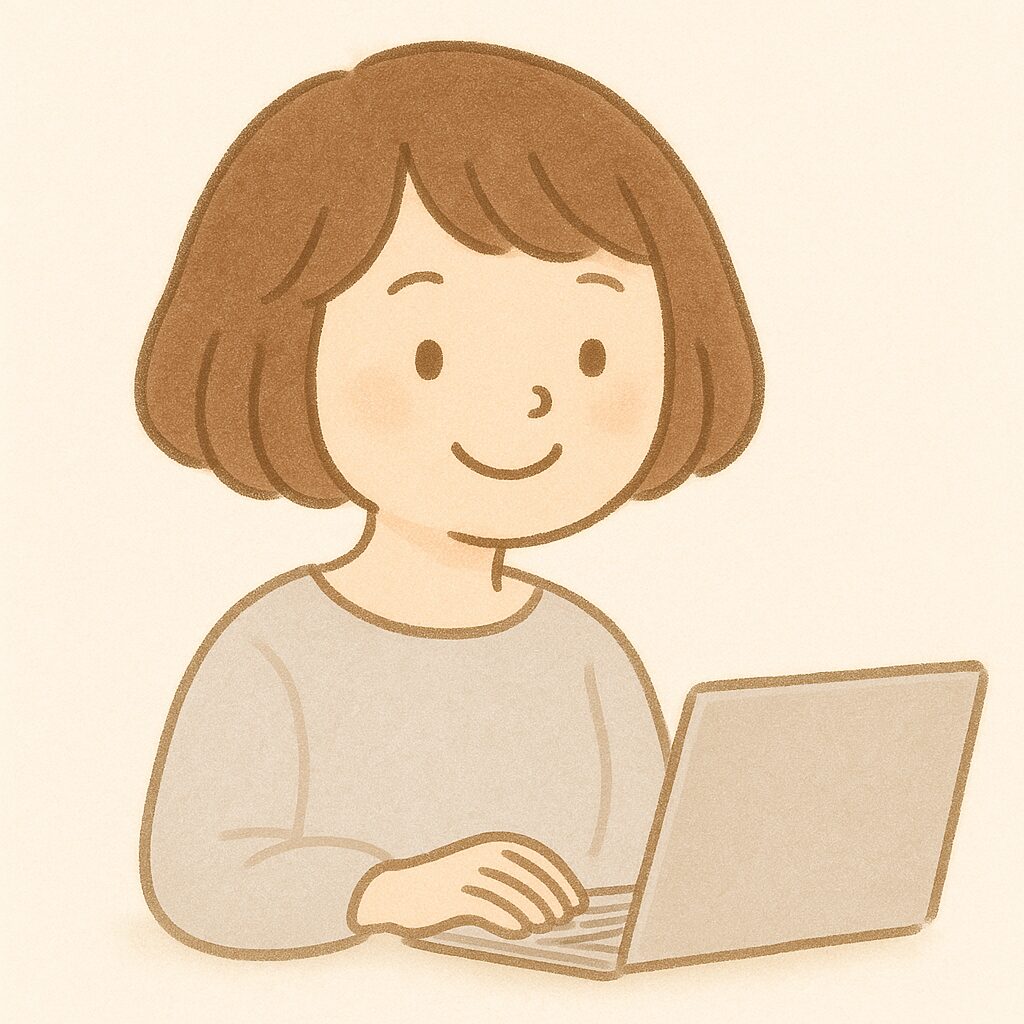
shiro(しろ)
・占いや心理学が大好きなブロガー
・MBTI・数秘術・パワーストーンを日々勉強中
・自分を知って、毎日をちょっと楽しく
・読むと元気になれる記事をお届けします
・パワーストーンや性格診断の記事も人気!

- 型ってつまらない?
- 一緒にいても盛り上がらない
そんな言葉を聞いて、少しショックを受けたことはありませんか?
自分がS型かどうかわからなくても、「現実的すぎる」「話が広がらない」と言われると、少し気になりますよね。
でも実は、“S型=つまらない”というイメージは誤解です。
MBTIのタイプを知ることで、コミュニケーションや人間関係の悩みがスッキリすることもあります。
また、HSP(繊細気質)とMBTIを組み合わせて理解することで、自分の強みや人との距離感がより明確になります。
→ HSP×MBTIで自分を深く知る方法
この記事では、S型がそう言われやすい理由と、N型との上手な関わり方を、心理学の視点からわかりやすく解説します。
目次
MBTIのS型とは?「つまらない」と言われる前に知っておきたい基本

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)は、人間の性格を16タイプに分類する心理学理論です。
その中でも「S型(感覚型)」は、物事を五感で捉え、現実を重視するタイプ。
では、S型とはどんな特性を持っているのでしょうか?ここでは基本から丁寧に見ていきましょう。
MBTIのS型(感覚型)の特徴と性格傾向
S型の人は、次のような特徴を持っています。
このような特徴から、S型の人は組織やチームにおいて「確実に物事を前に進める力」を担っていることが多いです。
S型とN型の違い|MBTIにおける情報処理スタイルの違いとは?
MBTIの中でも、S(感覚型)とN(直観型)の違いは、情報の受け取り方のスタイルに深く関わっています。
指標の違い(S型とN型の比較)
| 指標 | S型(感覚型) | N型(直観型) |
|---|---|---|
| 情報の捉え方 | 現実的・五感重視 | 抽象的・直感重視 |
| 好む話題 | 日常・具体的な出来事 | 未来・アイデア・哲学 |
| 判断基準 | 実績・経験・目に見える情報 | 可能性・直感・パターン |
| 思考の傾向 | 実務的・再現重視 | 創造的・発想重視 |
| 会話スタイル | 具体例や経験談が中心 | たとえ話・抽象的な話題が多い |
この違いが、後述する「会話のすれ違い」や「誤解」に大きく影響してきます。
関連:性格タイプ別に “完璧主義の傾向” を知るなら → MBTIタイプ別・完璧主義の特徴と対処法
S型が「つまらない」と言われるのはなぜ?誤解の理由と本当の魅力
MBTI診断でS型とされる人が、「一緒にいてつまらない」「話が広がらない」と言われてしまうことがあります。
しかし、それは本質的な欠点ではなく、N型との“認知スタイルの違い”にすぎません。
抽象的な話についていけない?S型の現実志向が誤解を生む理由
N型(直観型)の人は、「未来の話」や「意味を考える」「抽象的な問い」が好きな傾向があります。
たとえば、
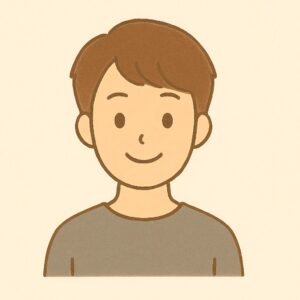
- 「時間って本当に存在してると思う?」
- 「もし自分が別の人生を歩んでいたら…」
- 「宇宙の果てってどうなってるんだろう?」
こうした話題にワクワクするのがN型です。
一方で、S型はこうした問いに対して、

- で、それって今の生活にどう関係あるの?
- そういうの考えてもキリなくない?
と感じてしまうことがあります。
この違いが積み重なることで、N型側が「話が噛み合わない」「話しててつまらない」と感じるケースがあるのです。
でもこれは、「S型がつまらない人」なのではなく、関心の方向性が違うだけ。
MBTIのS型とN型の会話が噛み合わない典型パターンとは?
N型は、日常会話にも比喩や抽象的な話を取り入れるのが好きです。
例:典型的なすれ違い会話
N型:「この前見た映画、なんか人生観変わった気がする」
S型:「へえ、で、ストーリーは面白かったの?」
または、
N型:「宇宙の始まりってさ、ビッグバン以前ってどうなってたんだろう」
S型:「それ今話す必要ある?」
このようなすれ違いが続くと、N型は「深い話ができない」「価値観が合わない」と感じやすくなります。
ただし、ここにも誤解があります。
S型が否定しているのではなく、「現実的に意味があるかどうか」に軸を置いて考えているのです。
MBTIのS型が「つまらない」と言われがちな原因の裏にある魅力と強み
「S型はつまらない」と言われがちですが、実はその性質は社会や人間関係の“土台”を支える存在として非常に重要です。
ここでは、S型(感覚型)が持つ本来の魅力と強みを見ていきましょう。
S型の実行力と地に足のついた行動力
S型の最大の魅力のひとつは、言葉だけで終わらせない“行動力”と“実現力”です。
この「実行力」があるからこそ、夢見がちなN型の構想も現実になるのです。
気配りと安定感で信頼されるMBTIのS型
S型は、人との関係性においても“現場感覚”を大切にするタイプ。
だからこそ、細かな気配りや丁寧な対応が自然と身についています。
つまり、派手ではないけれど“信頼される存在”なのです。
音楽趣味に性格が反映されることも多いです → MBTIタイプ別の音楽の好みとは?性格とジャンルの関係性
職場で重宝されるS型の安定性と再現力
S型は職場において、非常に頼りにされるタイプです。
なぜなら、彼らは「現実的に動ける」うえに「ミスが少ない」から。
実際、組織や職場では「N型が企画して、S型が実行する」という役割分担が理想的とされています。
MBTIのS型とN型が分かり合うためにできること
「S型は現実的」「N型は理想的」と言われますが、どちらが正しい・優れているということではありません。
違いを知り、相手の見方を尊重することが、分かり合う第一歩です。
S型・N型それぞれの価値観を理解する
S型の価値観
- 目の前のことをコツコツ積み上げたい
- 確実な成果・実績を重視
- 日々の安定と現実の改善に関心がある
N型の価値観
- 可能性を広げることにワクワクする
- 未来の構想や創造的な話が好き
- 「意味」や「意図」に敏感で深読みする傾向がある
このように、目指している方向が違うだけなので、「相手は間違っている」と思う必要はないのです。
顔や雰囲気に性格が表れることもあるので興味があれば → MBTI容姿ランキングTOP5|タイプ別に見た外見の魅力と特徴
S型がN型との会話ですれ違わないための工夫
S型がN型とよりよい関係を築くには、以下のような工夫が有効です。
N型がS型の発言を“否定”と受け取らないために
一方で、N型側にも理解してほしいポイントがあります。
S型の立場からすると…
- 抽象論は“現実逃避”に見えることがある
→ 実用性が見えないと、話に入りにくいのです。 - 「現実性へのこだわり」は否定ではなく“配慮”
→ 相手が傷つかないように、うまくいくように…と考えているからこそ慎重なのです。 - 論理的プロセスを大切にしている
→ 直感よりも、筋道が立っていると安心します。
つまり、S型は「冷たい」のではなく、「優しくて慎重」なだけなのです。
MBTIのS型はクリエイティブじゃない?よくある誤解と質問Q&A
S型とN型の違いについて理解が深まっても、「それでもこんな疑問がある…」という声もよく聞かれます。
ここでは、特によくある誤解や質問にQ&A形式でお答えします。
Q. S型に創造性はないの? → 実は「形にする力」が強み
A. いいえ、それは大きな誤解です。
S型は確かに「突飛なアイデア」や「空想的な発想」を得意とするN型とは異なりますが、“現実を形にする創造性”に優れています。
たとえば、美しい写真を撮って編集する人、こだわりのレシピを追求する人、ミシンや工具を使って作品を作る人などは、まさにS型的なクリエイターです。
「空想する」のではなく、「手を動かしてカタチにする」のがS型の強み。
これも立派なクリエイティブです。
Q. N型との相性は悪い? → 補完関係で最強タッグにも
A. 実は、補い合える“最強の組み合わせ”になることもあります。
S型とN型は、「思考の方向性」が違うため、確かに最初は戸惑いやすいです。
しかし、違いを理解していれば最強のパートナー関係になります。
つまり、最初は「違い=ズレ」でも、お互いを知ることで「違い=強み」になるのです。
- 性格分類をMBTI以外でも理解したい方は → オーシャン性格診断とは?5因子で知る自分
- 内向的な性質で行動しづらさを感じたことがある方へ → 陰キャが美容院に行きづらい理由と克服する5ステップ
ちなみに、自分に合うパワーストーンを通して性格や内面と向き合う人も増えています。
MBTIで自分の傾向を知ったあと、「それに合う石があるなら知りたい」と思う方も多いようです。ブルートパーズは魔除けに効果あり?意味・効果 をチェックして、自分の“エネルギータイプ”とパワーストーンの相性を考えてみてください。
まとめ|MBTIのS型は「つまらない」どころか現実を支える縁の下の力持ち
「S型はつまらない」と言われても、それは“あなたの価値”の否定ではありません。
むしろ、現実を支え、周りを安心させられるのがS型の最大の魅力。
N型のような発想力と、S型の実行力。
そのバランスこそが、世界を動かしているのです。
あなたらしい感覚と優しさを、誇りに思ってください。
関連記事
- 性格×波動で読む石選び → イエローサファイアの石言葉
- 直感力を高めたいなら → パープルサファイアの石言葉
- 癒しや愛情のサポートを求めるなら → ピンクムーンストーンの効果
あなたのMBTIタイプに合うパワーストーンはどれ?
性格診断×パワーストーンの組み合わせを知りたい方は、
→ パワーストーン記事一覧はこちら